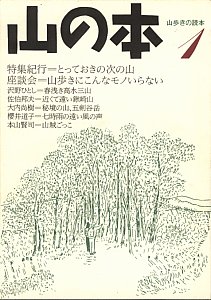Be-Pal (ビーパル) (小学館)
 ビーパル 創刊号
ビーパル 創刊号
日本のアウトドア雑誌のスタイルを変え、ひとつの形を作ってしまった雑誌だ。
創刊号は1981年7月号。
当時、小学館から新しいアウトドア雑誌が出るという噂を聞いて、期待して待ち構えるようにして手に取った創刊号を見てびっくり。
これがアウトドア雑誌か!?
Outdoorの硬派なイメージの微塵もない、その表紙!
山や森の風景写真、またはバックパッキングやクライミングやカヌーのアクティブな写真をイメージしていた眼に飛び込んできたのは、 ほとんど何の脈絡もない、水着のおねえちゃんの、しかも顔さえ出てない胸だけ強調した写真で、Playboyか平凡パンチかという 斬新な、または異常な表紙だった。
ちなみにおねえちゃんは第3号でやっと顔が出た (^^)
それまでアウトドアといえば、伝統的登山アルピニズムの流れか、またはソーローやビート的文化などの流れをくむアメリカの哲学的なバックパッキングムーブメントを意識したものか、という2大勢力だったのだが、ここは違った。
こういう、独特の「軽さ」はそれまでのアウトドア系雑誌には見られないものだった。
記事内容にしてからが、キャンピングカーで埋立地で読書を楽しむとか、公園でゴム動力飛行機を飛ばそうとか、クライミング用品を駆使して木登りをするとか、スーツの下にフライベストを着て会社帰りに釣りをするとか、およそ従来考えもしなかったバカバカしいような記事がたくさんあって、当時は理解しがたいものがあった。
それと、そういった記事の合間に必ず出てくる小物グッズの価格付き紹介、細かいコラムを集めたページの作りなど、 どう見ても当時画期的だった、カタログ・コラム雑誌「ポパイ」の手法をアウトドアにも取り入れたようなやり方だったように思われる。
従来の硬派登山人間にとっては、恐ろしく散漫で軟弱な雑誌としか言いようのないものだったが、敷居の低いその世界はたちまち多くのファンを生み、業界No.1雑誌になってしまったのだ。
アウトドア、キャンプ、アウトドアファッションがこんなに一般化したのは時代の流れだが、Be-Palはそういったアウトドアの大衆化の流れと完全に一体化して、またスタイルを作りながら現在に至ったのだろう。
この流れの元祖となり、一方の歴史を作ってきたことで、その後どんなに多くの雑誌が出てきても、みんなこの雑誌のエピゴーネンに 見えてしまう宿命が一時期はあったようである。
きっと、アウトドア雑誌の歴史の中では、OutdoorとBe-Palの2誌は永遠に本家と元祖でありつづけるのだろう。
 ビーパル 2号
ビーパル 2号
 ビーパル 3号
ビーパル 3号